内科
- HOME
- 内科
お知らせ
◆2025年度インフルエンザワクチン接種のお知らせ(自由診療)
- (Web予約開始日)
- 2025年9月22日(月)~
- (接種期間)
- 2025年10月1日(水)~2026年1月31日(土)
- (接種料金)
-
- 6か月以上3歳未満
- 1回 2,300円(税込)
- 3歳以上~65歳未満
- 1回 3,000円(税込)
- 65歳以上
- 各市町村から通知記載されている金額
・インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンの接種間隔に関する規定がなく、同時接種が可能です。なお、インフルエンザワクチン以外のワクチンについては、現行通り、13日以上の間隔をあけて接種することになります。
・インフルエンザワクチンを予約されている方で、新型コロナワクチン同時接種をご希望の方は、来院時受付でお申し出下さい。
・コロナワクチンは予約制ではありません。
(65歳未満の方は完全予約制です)
①
事前Web予約必須、電話予約不可
Web予約の際は、毎年新たにご利用登録が必要です。まず初めて来院される方又は診察券をお持ちの方のどちらかをクリックして登録をお願い致します。次にインフルエンザ予約からご予約をお願い致します。
②ご予約はWEBにて、前日の23:59まで可能です。当日のご予約はお受けしておりません。ご注意ください。
③予約時間を過ぎてもご来院されない場合はキャンセルとさせて頂きます。
(65歳以上の方はご予約不要です)
各市町村からの通知(予診票)を必ずご持参ください。
(予診票について)
①
事前に予診票を記入の上、ご来院下さい。
(65歳未満の方の予診票はダウンロード可能です)
体温の記入も忘れずにお願い致します。
②
16歳未満の場合は、
保護者のご署名をお願いします。
16歳以上から
ご本人の署名が必要になります。
③
18歳未満の方は
原則、保護者の同伴が必要です。やむを得ない理由で保護者が同伴できない場合は、
予診票の「本人(保護者)記入欄」に、ご本人と保護者の方と連名で署名をして頂き、保護者の方の連絡先も横にご記入をお願いします。
予診票の
記入もれの無いようにお願いします。
(注意事項)
①
必ずマスクを着用しご来院ください。
②
緊急の患者さんや処置、検査などの対応でお待たせすることや、順番が変わることをご了承ください。
③
待合室の混雑状況によっては
外でお待ちいただくか、車内でお待ちいただくこともありますのでご了承ください。
④
お支払は現金のみです。(カードや電子マネーはご利用できません)
(おつりの無いようにご準備お願いします。)
◆2025年度新型コロナワクチン接種のお知らせ(自由診療)
- (接種期間)
- 2025年10月1日(水)~2026年3月31日(土)
- (接種料金)
-
- 12歳~65歳未満
- 1回 16,500円(税込)
- 65歳以上
- 各市町村から通知記載されている金額
・新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの接種間隔に関する規定がなく、同時接種が可能です。なお、インフルエンザワクチン以外のワクチンについては、現行通り、13日以上の間隔をあけて接種することになります。
・インフルエンザワクチンを予約されている方で、新型コロナワクチン同時接種をご希望の方は、来院時受付でお申し出下さい。
・コロナワクチンは予約制ではありません。
(予約制ではありません)
新型コロナワクチンにつきましては12歳以上の全ての方が対象です。
必ず下記の時間内にご来院下さい。
(来院時間)
| 午前 | 9:00~11:30(月・火・水・木・金・土) |
|---|---|
| 午後 | 14:00~16:30(月・火・水・金) |
(接種後の待機時間)
新型コロナワクチン接種後15分~30分
(Drの判断によっては、30分待機の場合もあります。)
(予診票について)
①予診票のダウンロードはできません。
②12歳~65歳未満の方は来院時に予診票をお渡しします。
③65歳以上の方は各市町村から通知された予診票を記入の上必ずご持参ください。記入漏れのないようにお願いします。
(注意事項)
①必ずマスクを着用しご来院ください。
②緊急の患者さんや処置、検査などの対応でお待たせすることや、順番が変わることをご了承ください。
③待合室の混雑状況によっては外でお待ちいただくか、車内でお待ちいただくこともありますのでご了承ください。
④お支払は現金のみです。(カードや電子マネーはご利用できません)
(おつりの無いようにご準備お願いします。)
◆発熱外来お知らせ
当院では、受診歴の有無にかかわらず、発熱患者様の受け入れを行っております。
今後、発熱のある方で当院受診希望の方は事前に電話連絡していただき、決められた時間に当院裏に設けました発熱外来専用出入口においで下さい。
◆当院では、マイナンバーカードが保険証として使えます。
受診の際、マイナンバーカードをお持ちいただければ、同意することで
健診情報や処方されたお薬の情報等を見られるので医師もそれらの情報に基づいた診療が行えます。
内科【受付時間】
R4.9.1~
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 月・火・水・金 | 9:00~12:30 | 2:00~5:30 |
| 木・土 | 9:00~12:30 | 休診 |
内科診療時間(理事長 丹尾 裕 先生)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | 休 |
| 14:00~18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | ◯ | 休 | 休 | 休 |
休診日:日曜・祝日
午後休診:木曜・土曜
内科診療時間(院長 丹尾 多希 先生)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | 休 |
| 14:00~18:00 | ◯ | ◯ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休診日:日曜・祝日
午後休診:水曜・木曜・金曜・土曜

風邪(鼻づまり、鼻やのどの粘膜の乾燥、くしゃみ、鼻水、のどが痛む、せきが出る。などの症状)
風邪は、鼻からのどまでの上気道を中心とする部分に、ウイルスや細菌が感染して急激に起こる炎症です。
実際に風邪をひくと、気管や気管支などの下気道にも炎症が広がっていく場合も少なくありません。原因になる病原体はたくさんありますが、その80~90%はウイルスです。
疲労やストレス、睡眠不足、栄養バランスの偏り、寒さ、乾燥などの要因が重なると発症しやすくなることが知られています。

インフルエンザ
インフルエンザウイルスが病原で起こる疾患です。A型、B型、C型の3種類があります。潜伏期は1~3日くらいで、患者が咳をしたりするとウイルスが空中を浮遊し、それを人が吸い込むことで感染します。治療は症状出現後2日以内に開始します。
インフルエンザワクチンの予防接種(※)である程度は防げますが、その年によって流行する菌の型が違うため万能ではありません。体の弱い人は、流行している時に人混みに出るのを控えた方がよいでしょう。
(※)は自費料金になります。料金は料金表をご確認ください。

糖尿病
糖尿病は、食事で摂った糖をエネルギーに変えるときに必要なホルモンであるインスリンの異常から起こる病気です。インスリンの産生や分泌が不足したり、インスリンが十分に働かなくなると、血液の中にブドウ糖が溜まり糖尿病の状態となります。
糖尿病を放置しておくと、網膜症、腎症、神経障害などの合併症が起こります。食事療法や運動療法、薬物療法などをきちんと行い、血糖値をうまくコントロールして合併症を防ぐことが重要です。

脂質異常症(従来の高脂血症)
脂質異常症とは、血液中にコレステロールや中性脂肪などの脂質が異常に増加した状態をいいます。
長く続くと動脈硬化が生じ、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞、 閉塞性動脈硬化症などの病気を起こします。
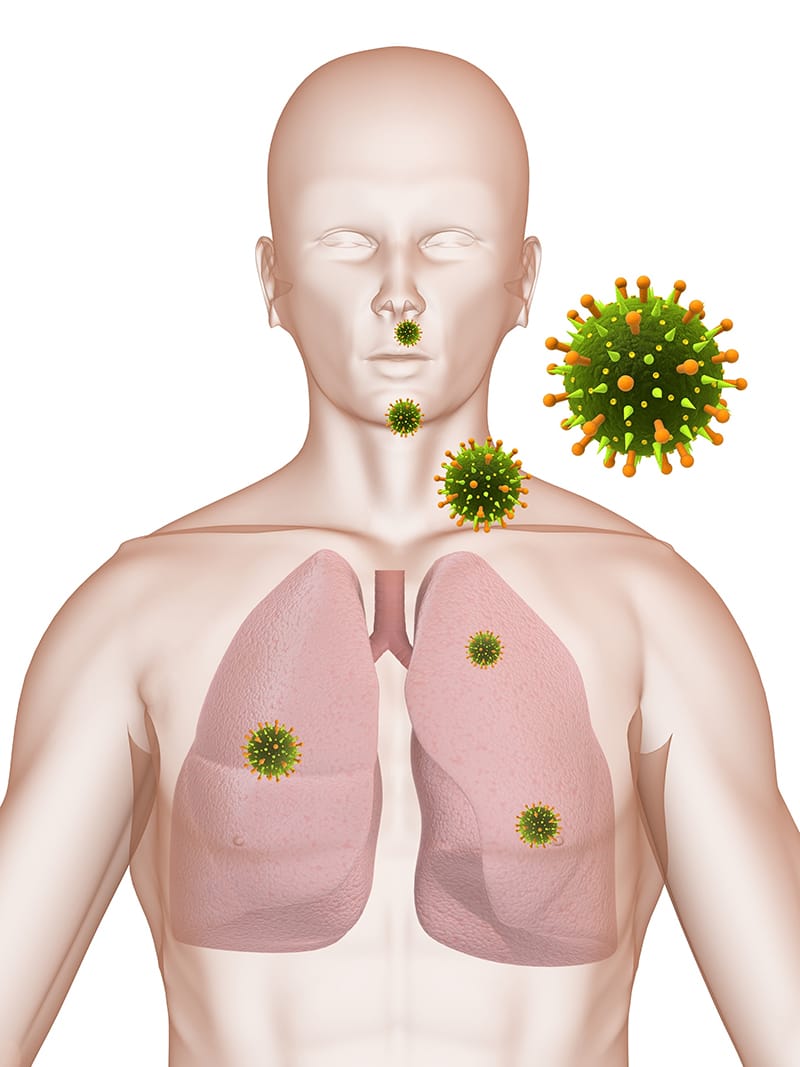
肺炎
肺炎とは、病原微生物や細菌が肺に感染し、炎症を起こす病気です。発熱、倦怠感、咳、胸痛などの症状が出現します。
特に病気をもっていない健康な人が、普段の生活や町の中で発症する(市中肺炎と呼ばれる)こともあれば、病院内で何らかの病気をもった人に発症する場合(院内肺炎)もあります。1.細菌性肺炎、2.ウイルス性肺炎、3.マイコプラズマ肺炎、などに分類されます。それぞれに肺炎を引き起こす病原体が異なります。
細菌性肺炎の原因一つは肺炎球菌です。そのほかインフルエンザ菌、ブドウ球菌、肺炎球菌、緑膿菌、溶血性連鎖球菌などが原因となることもあります。
ウイルス性肺炎は、細菌よりも小さい病原体であるウイルスに感染して起こります。麻疹ウイルス、水痘・帯状疱疹ウイルス、サイトメガロウイルスなどのウイルスが急速に増殖することによって起こる場合もあります。
マイコプラズマ肺炎は、市中肺炎としては肺炎球菌によるものより多くマイコプラズマという病原微生物に感染して起こります。病原菌の種類によって有効な抗生物質を選びます。

甲状腺機能低下症
甲状腺ホルモンの不足による病気です。慢性的に甲状腺に炎症が起きている橋本病(慢性甲状腺炎)は、女性の10~20人に一人がかかっているとも言われています。その他、先天的に甲状腺ホルモンが欠乏するクレチン病などもあります。
症状は(倦怠感、徐脈、便秘、むくみなど)老化に似ているため、病気と気づかない人もいます。また、医師の診察においても、他の病気と間違われやすいのが特徴です。

鉄欠乏性貧血
鉄欠乏性貧血は、鉄が不足するために起こります。
貧血の中でいちばん多い病気で、 特に女性に多く、日本では成人女性の約5~10%がこの病気だといわれています。
原因は、鉄分の摂取不足または体内での需要増大、体外に失われる鉄分量の増加などです。ダイエットのための食事を続けると、鉄の欠乏を起こすことがあるので注意が必要です。鉄分の需要が増えるのは思春期や成長期で、体が大きくなるため血液量も増え、鉄分がさらに必要になります。